お子さんが知的障害や自閉症、発達障害と診断されたとき、「障害者手帳を取ったほうがいい?」と悩む方は少なくありません。障害者手帳は、生活や支援の幅を広げる大切な制度ですが、その一方で「取るとデメリットはないの?」という不安や心配もあるかと思います。
今回は、障害者手帳の取得方法と、メリット・デメリットについて、まとめます。
1. 障害者手帳とは?
障害者手帳には大きく分けて3種類があります。
1. 身体障害者手帳
身体の機能に障害がある場合(視覚、聴覚、肢体不自由など)に交付されます。
2. 療育手帳(知的障害)
知的障害のある方に交付されます。名称や等級区分は自治体によって異なり、「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ばれることもあります。
3. 精神障害者保健福祉手帳
発達障害や精神疾患(うつ病、統合失調症など)などで長期的な支援が必要な場合に交付されます。もちろん、発達障害のみの場合でも取得は可能です。
知的障害や自閉症、発達障害の場合は、主に療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を取得するケースが多いかと思います。
2. 障害者手帳の取得方法
(1)まずは医師の診断
取得には、障害の状態を証明する医師の診断書が必要です。
・療育手帳 → 療育センターや児童相談所での判定
・精神障害者保健福祉手帳 → 指定医の診断書
発達障害の場合は、発達障害を診断できる精神科・児童精神科、発達外来などで診断を受けます。
ちなみに、大阪では、児童相談所ではなく、大阪府独自制度で「子ども家庭センター」という名称になっています。児童相談所ではないので、お間違えのないようにお願いできたらと思います。
(2)申請先と必要書類
申請先は「お住まいの市区町村役所(福祉課や障害福祉課)」です。
必要書類の例:
・申請書(窓口でもらえます)
・診断書または判定書
・顔写真(サイズ指定あり)
・印鑑(自治体によって不要な場合あり)
・マイナンバーカードや身分証明書
(3)判定と交付
提出後、審査や判定会議が行われ、結果が通知されます。
申請から交付までの期間は、療育手帳で1〜2か月程度、精神障害者保健福祉手帳で1〜3か月程度が一般的です。
交付時には役所で手帳を受け取り、利用開始できます。
3. 障害者手帳のメリット
① 公共料金・交通費の割引
・バス・電車・タクシー料金の割引(等級や事業者によって異なる)
・高速道路料金の割引
・携帯電話基本料金の割引
・NHK受信料の免除や減額
政令指定都市や中核市などでは、例えば市バス(市営の地下鉄など)が無料になる自治体も多いと聞きます。
交通費の無料や割引は、移動がある方にとっては大きなメリットであるように思います。
② 医療費や福祉サービスの優遇
・医療費助成(自治体による)
・障害福祉サービスの利用(就労支援、生活介護、放課後等デイサービスなど)
・補装具や日常生活用具の給付
障害者手帳を窓口で見せることで、手続きがスムーズになります。
また、利用できる内容もさまざまにあるため、市区町村役所で聞いてみるのもおすすめですし、利用できる医療や福祉のサービス内容を自治体ごとにわかりやすくまとめた冊子などもあるかと思います。
③ 就労面での支援
・障害者雇用枠での就職活動が可能
・ハローワークでの専門相談員による支援
・職業訓練校での優先受講や支援体制
わかりやすいのは、障害者雇用で就職が目指せることで、職場で支援や配慮のある環境下で働くことが可能になります。また、退職後の失業給付も基本的には待機期間なしですぐに給付が受けられます。
④ 税制面での優遇
・所得税・住民税の障害者控除
・自動車税・軽自動車税の減免(条件あり)
・贈与税・相続税の優遇
・公共料金の割引(NHK受信料、携帯電話基本料金など)
税制面の優遇に加えて、公共料金などの割引も複数あるので、詳しくはそれぞれの利用サービスにて、問い合わせをしてもらえたらと思います。
⑤ 社会的理解の促進
手帳を持っていることで、学校や職場などで配慮を受けやすくなるケースがあります。
実は、これが中長期的には一番のメリットなように思います。
特に発達障害など外見でわかりにくい障害の場合、手帳があることで支援の必要性を第三者に説明しやすくなります。
最近は、手帳とともに、ヘルプマークをかばんにつけて周りの人にさりげなく理解してもらう動きも増えてきたように思います。
4. 障害者手帳のデメリット
① 個人情報の開示リスク
就職や進学の際に、手帳所持を伝える必要がある場合があります。
そのことで不安や偏見を感じるケースもあります。
② 更新や再判定の負担
療育手帳は一度取得すると更新不要な場合もありますが、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。
再診断や書類提出の手間がかかります。
そのため、かかりつけの精神科を見つけておき、主治医との関係性をつくるためにも定期通院をしておくことで障害者手帳の更新もスムーズかと思います。
③ 支援制度が自治体ごとに違う
同じ手帳でも、市区町村によって使えるサービスや割引内容が異なります。
引っ越しで利用できなくなる支援もあるため、事前確認が必要です。
実際に、僕の知り合いの方も関東から関西に引っ越しをされ、利用範囲と内容が一部変わったとおっしゃっていました。
④ 「手帳があるから支援を受けられる」とは限らない
手帳はあくまで「支援の対象であることを示す証明書」です。
実際に利用できるサービスは、別途申請や調査などが必要な場合もあります。
ただ、証明書があることで申請や調査はスムーズに進めやすいですし、主治医との関係性もできていれば、困ったときには主治医にも意見をしてもらうことで、手続きもよりスムーズかと思います。
5. 取得前に考えておきたいこと
・今すぐ必要な支援は何か?
・将来の就労や進学での活用予定はあるか?
・本人や家族が手帳所持をどう受け止めるか?
また、お子さんが成長して自己決定をする年齢になったら、一緒に話し合うことも大切です。
「手帳を持つことは恥ずかしいことではない」というメッセージを、家庭内で共有できるとよいでしょう。
それに、精神の手帳は2年ごとの更新でもあるので、子どもが大人になり、社会人になり、自分なりの意見と考えで「次のタイミングで手帳の更新はしない」と決めるならそれもひとつの自己選択と自己決定でもあります。
実際、僕の知っている障害のある男性(30代)の方は、いろんな背景もあって、「更新しない」を選択した方もおられ、障害者雇用から一般企業で再就職され、元気にがんばっておられます。
6. まとめ
障害者手帳は、生活の選択肢や支援と配慮の幅を広げるための大切な制度です。
取得には診断や申請手続きが必要ですが、医療・福祉・就労・税制など、多方面でメリットがあります。
一方で、更新の手間や制度の地域差、更新や再判定の負担などには注意が必要です。
最終的には、「今のお子さんと家族にとって必要かどうか」を冷静に判断し、信頼できる支援者や医師と相談しながら決めることをおすすめします。
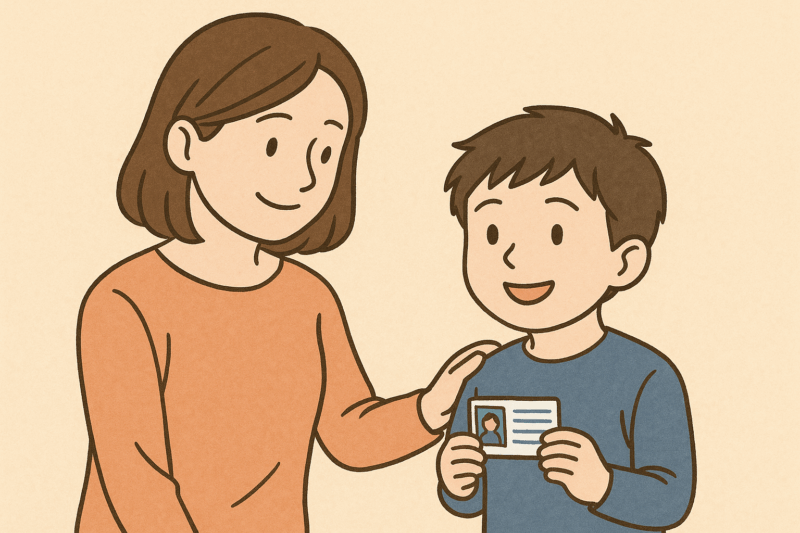
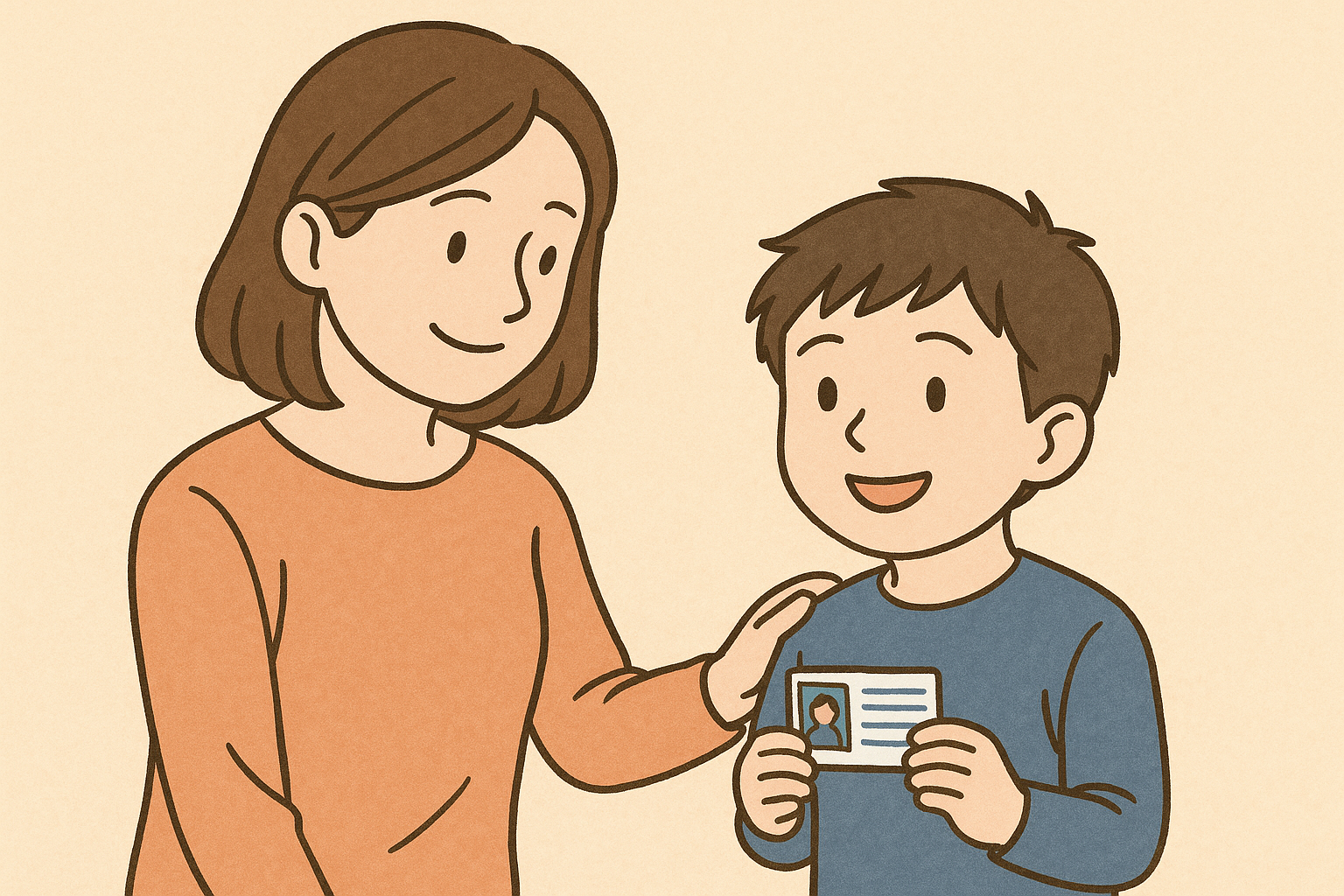

コメント