子どもが就職活動を始めるとき、親として「どうサポートすればいいのか」と悩む方は多いものです。
特に、近年は就職活動は早期化し、働き方の多様化もあって、就職活動の進め方もさまざまになっています。親世代の経験がそのまま通用しない場面も多くなったのかもしれないです。
そこで今回は、親ができる就職活動のサポートについて、具体的な方法を解説します。
子どもの意思を尊重する
就職活動サポートの第一歩は、当たり前かもしれないですが、まずは子どもが自分の意思で進路を選べる環境をつくることです。
親の経験や価値観を押し付けず、まずは子どもの考えをしっかり聞くことが大切です。
・悪い例:「そんな業界はやめておきなさい」
・良い例:「その会社に興味を持った理由は?」
親の焦る気持ちはなんとか置いといて、子ども自身が考えるきっかけを与えることが、長期的な成長につながっていきます。
信頼できる情報収集を手伝う
今の就活は情報が多く、何を信じるべきか迷いやすい時代。
ネットで調べるだけでも、山盛り出てきて取捨選択がとっても大変です。
親が企業選びを代行する必要はありませんが、信頼できる情報源を一緒に探すサポートは有効です。
・大学のキャリアセンターからの就職情報(最近はスマホで見やすくなってます)
・就職情報サイト(障害者雇用専門のウェブサーナやクローバーナビなど)
・ハローワークや新卒応援ハローワーク
・企業の公式採用ページや説明会情報
例えば、障害者雇用の専門サイトのウェブサーナでは、再来年卒業の学生さん向けに「プレサーナ」という独自サイトにて、インターンシップや会社説明会の情報をまとめています。
上場企業などの大手企業が多く参加していて、コロナ以降はオンラインも多くなり、オンラインでの参加もしやすくなったのも特徴です。
子どもが必要な情報を効率よく入手できるよう、親が「情報の交通整理役」になることがポイントですし、キャリアセンターや就労支援機関に探し方を聞いて、それを子どもと一緒に探すことも良い方法かと思います。
障害者雇用の仕組みを理解する
障害者雇用枠の採用は、一般枠と比べて選考方法や働き方が異なることがあります。
・書類選考や面接の回数が少ない場合がある
・採用後も配慮を前提にした職務設計がされる
・給与や雇用形態(正社員・契約社員)が企業ごとに異なる
ポイントとして
・ハローワークの「専門援助部門」は障害者雇用求人の情報が豊富(新卒ハローワークも情報豊富)
・障害者職業センターでは職務適性評価や準備訓練の機会がある
・大学の障害学生支援室は就職活動の配慮申請や企業との調整に協力してくれる
・卒業学年であれば、地域の就労移行支援事業所を利用できる(就活サポートや定着支援が受けられる)
面接・説明会参加のサポート
障害の特性によっては、会場までの移動や事前準備が負担になることもあります。
・会場までの経路確認や所要時間の計測
・公共交通機関の混雑時間を避ける計画
・模擬面接の練習相手
・配慮事項を簡潔に伝える練習
また、注意点は、親が面接に同席する場合は企業や支援機関と事前に相談しましょう。
本人の自立性を損なわないよう、必要な場面だけにサポートを絞ることが大切です。
例えば、会社見学やインターシップを予定しているなら、休みの日を使って子どもと一緒に事前に通勤経路を調べてみる、実際に会社まで調べた経路を使って行ってみて予行練習をする、といったようなサポートも親としては必要なことかと思います。
精神的な安心感を与える
就職活動では、不採用や不本意な結果が続くことも珍しくありません。
そんなときこそ、親の言葉が大きな支えになります。
• 「あなたの良さは必ず誰かに伝わる」
• 「挑戦したこと自体が素晴らしい」
• 「焦らず、自分のペースで大丈夫」
無理に励ますよりも、じっくり話を聞いて寄り添うことが大切ですし、就職活動は、子供と会社のご縁で成り立つものでもあるので、数撃ちゃ当たると言うわけではないですが、数をこなすことでご縁に恵まれると言うこともあると思うので、そんなことも子供との会話で話題にしてもらえたらと思います。
それに本人と職場の相性もとても大切です。相性の良い職場であればきっと長く働けます。相性の良い職場を見つけるには、会社見学やインターンシップなど職場を実際に見ることで、相性の良し悪しも本人なりに判断できることもあるため、ある意味で時間をかけながら、就職活を進めていくことも1つであることも子供との会話の中で話をしていってもらえたらと思います。
専門家を頼ることを促す
新卒で障害者雇用を目指す就職活動では、本人の努力と周囲のサポートの両方が欠かせません。
親の役割は、決して「代わりにやること」ではなく、本人が自分の力を発揮できるよう環境を整えることです。
そして、その環境づくりにおいては、就労支援機関の職員や大学の支援室、ハローワークなど、専門家とつながることが最大の武器になります。
実際に専門家の人が職場に行って、環境調整をしてくれ、本人に合った環境作りをサポートしてくれるのも、また専門家による人的サポートの魅力と思います。
できるなら、就職活動の最中から専門家に継続的に相談していき、進捗を一緒に確認してもらいながら適宜アドバイスをしてもらい、どんな職場が相性が良いか、働いた後にどんなふうに働いていけば良いかなどを専門家を頼って、就職活動と就職後のことを一緒に考えていく事は必要なことかと思います。
まとめ
就職活動サポートで大事なのは、「親が代わりに動くこと」ではなく、子どもが自分の力で未来を切り開けるよう環境を整えることです。
それに、子どもが専門家の人などの親とは違う誰かを頼りながら将来を自分なりに考えていくためのきっかけを作るのも大人になるための大切なプロセスでもあると思います。
就活は、お子さんにとっても苦しい時期になるかもしれません。
でも、苦しい時期があるからこそ、親や周りの県警者を頼ろうとする子どもの気持ちも芽生えるタイミングでもあり、相談すること、誰かを頼ること、自分のペースで進めて良いことを学ぶ機会としても、とてもよい時期であるため、そんな意味も含めながら、親としてできることをサポートしてもらえたらと思います。
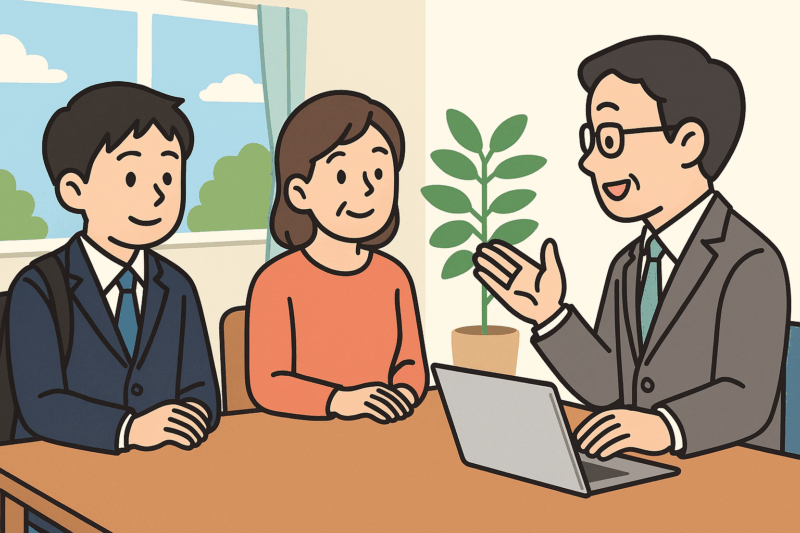



コメント