こんにちは。突然ですが、「うちの子、先のことがわからなくて不安そう…」なんてふうに感じたことってありませんか?
今日は、知的障害や発達障害のあるお子さんにとって、とても大切なキーワード「見通し」についてお話ししたいと思います。
見通しって何だろう?
「見通し」とは、これから起こることや未来の出来事を想像したり、理解したりすることを指します。たとえば「明日は学校に行って、そのあとおばあちゃんの家に行くよ」とか、「4月からは中学生になるんだよ」など、未来のことを頭の中で描けることって感じです。
私たち大人も、手帳やカレンダー、スマホのスケジュールアプリなどを使って、予定を立てたり、確認したりしていますよね。それがあるからこそ、「明日は忙しいから早起きしよう」「土曜日はゆっくりできるな」なんて、心の準備ができるわけです。
でも、知的障害や発達障害のあるお子さんの場合、この「見通しを持つこと」がちょっぴり苦手なことが多いのです。
見通しを持つのが苦手な理由
なぜ苦手なのかというと、知的機能や想像力の特性が関係しています。
・これから起こること(未来)
・経験したことのないこと(未経験)
・いつもと違うこと(変化)
こういった“曖昧なもの”や“はっきりしていないこと”は、イメージしにくく、不安につながっています。
一方で、
・実際に経験したこと(実体験)
・目で見てわかること(視覚情報)
・はっきりしていること(具体的な内容)
これらは理解しやすいとされています。だからこそ、「見通しを持つ」ということにサポートが必要!ってわけです。
見通しがあることで安心できる
子どもたちは、見通しがあると安心でき、落ち着いて行動することができます。
「今日は何があるのか」「これが終わったら何をするのか」など、流れがわかると見通しがもてえ安心でき、気持ちに余裕が出てきます。
逆に、何が起こるかわからない状態だと、強い不安を感じたり、パニックになってしまったりすることもあるかと思います。これは私たち大人でも同じです。突然予定が変わったり、説明もなく初めての場所に連れて行かれたら、誰だって戸惑います。見通しが持てないことはとてもストレスフルでもあります。
家庭でできる見通しのサポート
では、どうやって「見通しを持つ」に対してサポートをしていけばいいのでしょうか?
家庭でできる、いくつかのアイデアをご紹介します。
- スケジュールや予定表を使う
まずは、スケジュールや予定表を使って、1日の流れを見える形で伝えることが大切です。
たとえば前日の夜、「明日はこんな一日になるよ」とホワイトボードや紙に書いて見せてあげます。
【例】
• 8:00 起きる
• 9:00 学校に行く
• 15:00 帰宅
• 16:00 おやつ
• 17:00 お風呂
• 18:00 ごはん
• 20:00 寝る準備
持ち物や注意点も一緒に書いておくと、より安心につながることもあります。
- カレンダーで少し先の予定も見せる
「今日は何曜日?」「次のお休みはいつ?」など、少し先の予定も見えるようにすると、見通しを持つ練習になります。1週間の予定、月の行事、年間行事などを、カレンダーやポスターで一緒に確認するのもよいかと思います。
できたら、楽しみとなる家族でのお出かけなども、早めに伝えてみてください。
スケジュールやカレンダーに楽し身となる予定がたくさん書いてあると、見通しを持つことを好みやすくなるかと思います。
- 予定は「変わることもある」と伝える
ここがとても大切なポイントです。
予定は予定であって、「必ずその通りになるとは限らない」ということも、少しずつ伝えていけると理想です。
これもまた、経験とともに少しずつゆっくりと、理解していくことができるかと思います。
発達障害や知的障害のあるお子さんは、予定通りにいかないと強いストレスを感じることがあります。だからこそ、「予定はときどき変わるものだよ」という経験を、少しずつ積んでおくことが大事なように思います。
「今日は雨が降ってるから、公園はやめてお家で遊ぼうね」
「先生が急にお休みになったから、別の先生が来るよ」
そんなときは、スケジュールやカレンダーに変更点を書いて伝えて、「そういうこともあるんだな」と少しずつ思えるようになると、変更に対応できるようになっていくことができるようになるように思います。
- 経験を通じて「知っている未来」を増やす
経験は最大の見通しになります。
たとえば、一度行った場所なら「知ってる場所」になるし、一度やった活動なら「またできそう」という気持ちになります。
初めての場所に行くときは、事前に写真や地図を見せたり、「○○くんが行って楽しかったって言ってたよ」など、情報をたくさん与えることで、少しでも“曖昧”を減らす工夫に繋がります。
まとめ:見通しがある生活が、安心につながる
見通しを持つことができると、毎日の生活に安心感が生まれます。
そのために、家庭では
• 見える形で予定を伝える(スケジュールやカレンダー)
• 予定は変わることもあると伝える
• 実際の経験を積み重ねる
といったサポートを取り入れてみてください。
見通しが持てるようになると、次第に気持ちにも余裕ができて、自信にもつながっていきます。そして、ゆくゆくは変化にも対応できるようになっていく可能性もあります。
(ただ、ここは、特性上苦手なことでもあるので、親としては過度な期待のない範囲が望ましいかと思います。)
「先のことがわかる」って、すごく安心できること。
「見通し」をキーワードに、お子さんの毎日とこれからを、少しずつサポートしていってもらえたらと思います。
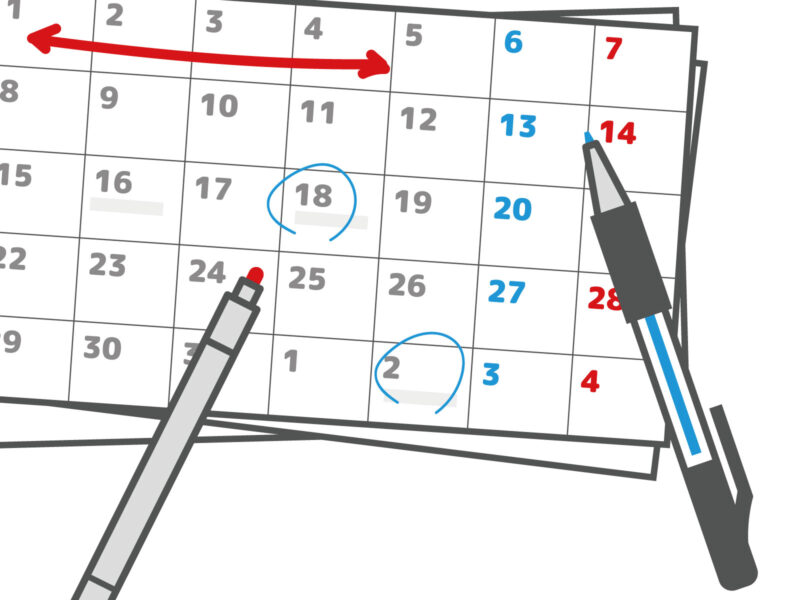
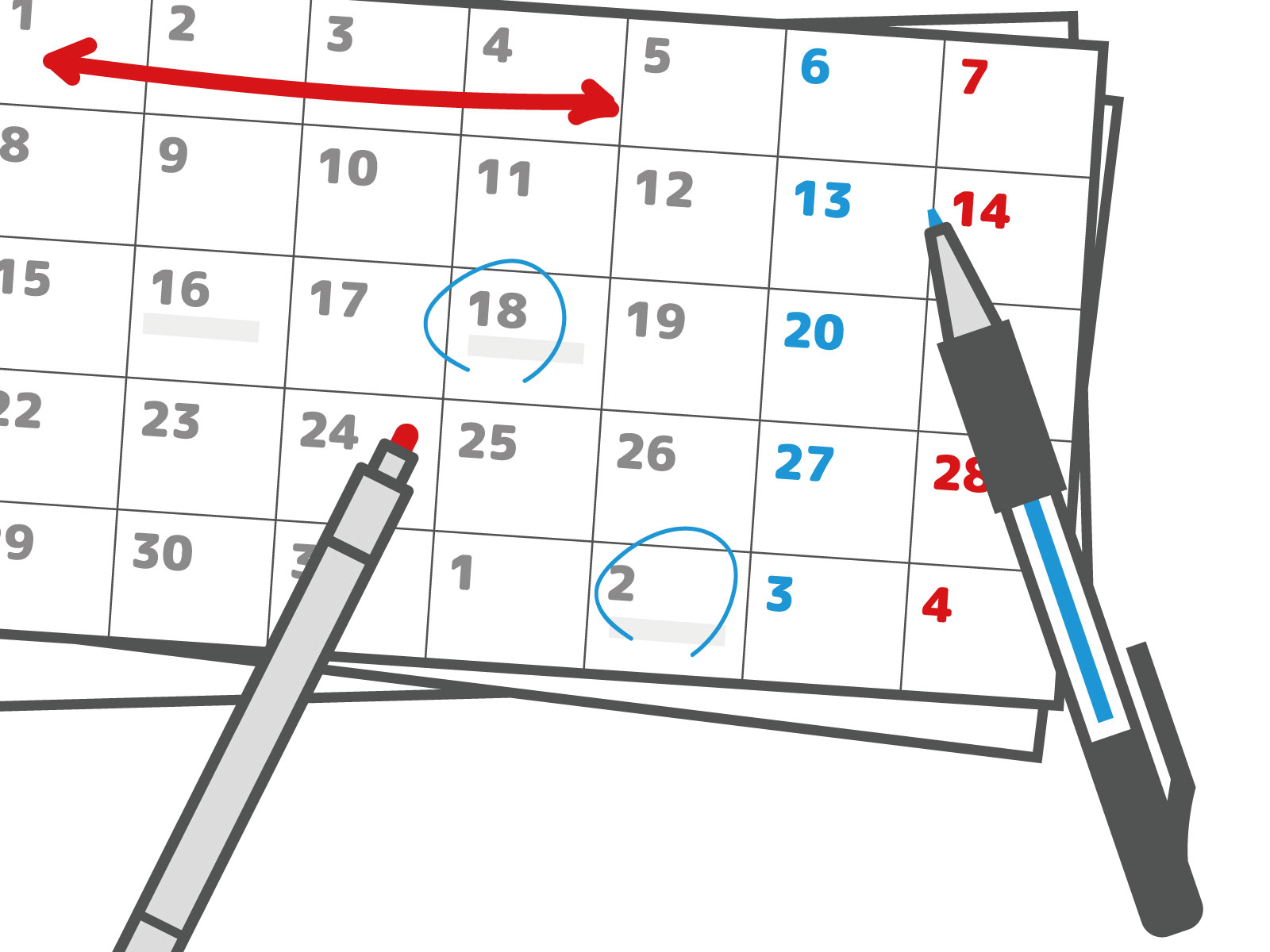


コメント